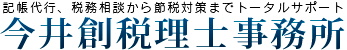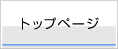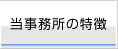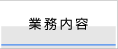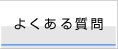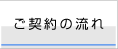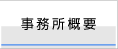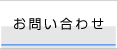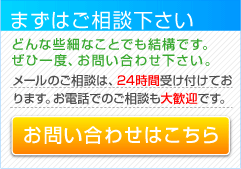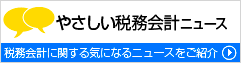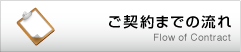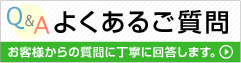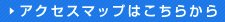�Ŗ���v�Ɋ֘A�����C�ɂȂ�j���[�X�����Љ�Ă��܂��B
�E��P�� �Ő�������j �@�l�ېŕ�(H28�N�x) �@�E��Q�� �Ő�������j ����ېŕ�(H28�N�x)
�E��R�� 28�N�̎����������@�l���q�� �@�@�@�@�E��S�� �Ő�������j �l�ېŕ�(H28�N�x)
�E��T�� 2016�N�x�Ő������F�ٗp���i��...�@�@�E��U�� �ǂ������D��H�⌾�ƈ�Y�������c��
�E��V�� ���Z�@�ւ́u��N���^�T�|�[�g...�@�@ �E��W�� ���ݗp�����̏��n�ƉېŎ��Ǝ�
�E��X�� �����Ŋz�̂Q�����Z�Ɨ{�q�@�@�@�@ �@ �E��10�� �^���}���ߐŁA���ɋK��
�E��11�� �����g��Ő��A������ƗD����...�@�@ �E��12�� ����29�N�x�Ő����� �l�����ېŕ�
�E��13�� ����29�N�x�Ő����� ���Y�ېŕ�...�@�@�E��14�� ����29�N�x�Ő����� �@�l�ېŕ�
�E��15�� �����̑����]���ōō��ق��R��... �@�@�E��16�� �ō��فF�ߐł̂��߂̗{�q���g��...�@
�E��17�� �@�葊�����ؖ����x���^�p�J�n���@�@�E��18�� �@�l����@�����b�g�ƃf�����b�g...
�E��19�� ����29�N4��1�����ݗ��E�ٓ�... �@�@�E��20�� H30�N1��1���Ȍ�̎葱�� �ی�...
�E�₳�����Ŗ���v�j���[�X�@��21��`�͂�����
�@���s�@�ł́A�����ی��_��̌_��҂̖��`��ύX���������ł́A�V���Ɍ_��҂ɂȂ����҂ɑ��鑡�^�̉ېł͂���܂���B
�@��̓I�ɂ́A�u�b�v�_��҂ł��ی������S�ҁA�u���v��ی��ҁA�u���v�ی������l�̏ꍇ�ŁA���̌�A�b���畸�Ɍ_��҂̖��`��ύX���A�����ی����S���邱�ƂɂȂ����Ƃ��Ă��A���`�ύX���܂łɁA�b�����S���Ă����ی��������z�ɂ��ẮA���ւ̑��^�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�����`�ύX��̉ېł̎戵���Ɩ��_
�@��L��ɂ����āA�@���ւ̖��`�ύX��A�b���S�O�ɕی��̖������}����ƁA���Y�����ی����͕������܂��B
���̏ꍇ�̕��̉ېł́A�����g�����S�����ی��������z�ɑΉ�����ی��������͈ꎞ�����Ƃ��Ẳېł��A�b�����S�����ی��������z�ɑΉ�����ی����͍b���瑡�^�ɂ��擾�������̂Ƃ��đ��^�ł̉ېł��܂��B
�@�܂��A�A���`�ύX��A�b�̎��S�O�ɔ�ی��҉������S����ƁA���Y���S�ی����͕�������܂��B���̏ꍇ�̕��̉ېł́A���S�ی����̓��A�������S�����ی��������z�ɑΉ�����ی����͈ꎞ�����Ƃ��Ẳېł��A�b�����S�����ی��������z�ɑΉ�����ی����͍b���瑡�^�ɂ��擾�������̂Ƃ��āA���^�ł̉ېł��܂��B
�@�Ȃ��A�B���`�ύX�i�b���畸�j���b�̎��S�ɂ���ĂȂ��ꂽ�ꍇ�ɂ́A���͐����ی��_��Ɋւ��錠���𑊑����ɂ��擾�������ƂɂȂ�A�b�̖{���̑������Y�Ƃ��đ����ł̉ېőΏۂɂȂ�܂��B
�@�ȏオ�ی��_��̖��`�ύX�Ɋւ���ېł̎戵���ł��B�������A���ۂ̐\���ł́A���`�ύX�Ɋւ��鎑�����\���ɐ�������Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��A���ی����̂��ׂĂ��ꎞ�����Ƃ��Đ\������Ă������A�@���\�肵�Ă����\�����s���Ă��Ȃ����Ⴊ�U�����ꂽ�悤�ł��B
������30�N1��1���Ȍ�̎戵��
�@���s�@�ł́A�ی���Ђ���Ŗ����ɒ�o�������i�x�������j�ɂ́A���`�ύX�Ɋւ�����A���̌_��҂̕����ی����Ɋւ�����͂���܂���B
�@�����ŁA����27�N�x�̐Ő������ŕ���30�N1��1���Ȍ�A�ی������̎x�����������ꍇ�A�܂��͌_��҂����S�����`�ύX���������ꍇ�ɂ́A�ی���Ђ͏�L����Ŗ����ɒ�o���邱�Ƃ��`���t�����܂����B
�@����x�A�ی��W�̏��ނ��m�F���A����̑Ή����l���Ă͂ǂ����Ǝv���܂��B

��29�N���o�L�����ؖ����̓Y�t�ȗ�
�@����29�N4��1����荑�Œ��ɒ�o����͏o���ɂ��ē�̌��������s���Ă��܂��B��́A�@�l�ݗ��͏o�����ɓo�L�����ؖ������̓Y�t���s�v�ƂȂ������Ƃł��B
�@����́A����25�N�Ɋt�c���肳�ꂽ�u���E�Ő�[IT���Ƒn���錾�v�Ɋ�Â��āA�s���g�D�̕ǂ��z�����f�[�^���p�ɂ��A�����T�[�r�X�����}�낤�Ƃ���u�o�L�E�@�l�ݗ����W�葱�̊ȑf���E�v�����Ɍ������A�N�V�����v�����v�Ƃ������f�I�Ȏ��g�݂̈�ł��i�@�l�ԍ����������̈�j�B
�@�@���Ȃł́A���̍s���@�ւƃI�����C���ŏ��A�g���ł���悤�ȐV�����o�L���V�X�e���̉^�p��32�N�x���ɊJ�n����\��ł��B���Œ��̓I�����C���Œ����o�L���̊��p��}�邽�߁A�W�Ȓ��Ƌc�_��i�߁A����29�N�Ő������Ŏ��̑Ώۓ͏o�����ւ̓o�L�����ؖ����̓Y�t���s�v�ƂȂ�܂����B
�P�D�@�l�̐ݗ��E���U�E�p�~���̓͏o��
�u�@�l�ݗ��͏o���v�A�u�O�����ʖ@�l�ɂȂ����|�̓͏o���v�A�u���v���ƊJ�n�͏o���v��
�Q�D�Ŗ����̋��߂ɉ����Y�t���Ă�������
�u�c�Ɠ��J�n�E�x�~�E�p�~�\�����v�i�����Ŗ@�A�������Ŗ@�A�Ŗ@���j��
���͏o���̒�o��̃����X�g�b�v��
�@�܂��A�����O�͈ٓ��O�ƈٓ���̑o���̏����Ŗ����ɒ�o���K�v�Ƃ���Ă����ٓ��͏o�����ɂ��ẮA����29�N4��1���Ȍ�̔[�Œn�̈ٓ����ɂ��A�ȉ��̑Ώۓ͏o�������o����ꍇ�A�ٓ���̏����Ŗ����ւ̒�o���s�v�ƂȂ�܂����B
�@�P�D������
�u�[�Œn�̕ύX�Ɋւ���͏o���v�A�u�[�Œn�̈ٓ��Ɋւ���͏o���v�A�u���^�x�����������̊J�݁E�ړ]�E�p�~�͏o���v�A�u�l���Ƃ̊J�ƁE�p�Ɠ��͏o���v
�@�Q�D�@�l��
�u�ٓ��͏o���v
�@�R�D�����
�u����ňٓ��͏o���v�A�u�[�Œn�̕ύX�Ɋւ���͏o���v�A�u�[�Œn�̈ٓ��Ɋւ���͏o���v
���n���ł͏]�O�ʂ�̎戵���̂��ߗv���ӁI
�@�����̎戵���͌��s�ł͍��ł݂̂ŁA�n���ł̓͏o���ɂ��Ă͓o�L�����ؖ����̓Y�t���o��͏]�O�ǂ���ł��̂ŁA�����ӂ��������B

���O���ɏ�������x�͍l����@�l����
�@�l���Ǝ҂��@�l��ݗ����邱�Ƃ��u�@�l����v�ƌĂт܂����A�l���Ƃ��O���ɏ���Ă���A��x�͍l����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ȃ��A�l����̂��Ƃ����ƁA�@�l����ɂ̓����b�g���f�����b�g�����邩��ł��B
����ʓI�ȃ����b�g
�@�P�D���^�����T�����g����F�@�l��������ĉ�Ђ��狋�^�����悤�ɂ���A�o�c�Ҏ��g�̏����łŋ��^�����T�����g���A�ߐłɂȂ�܂��B
�@�Q�D����ł��ő�Q�N�ԖƏ������F���{����1,000���~�����̖@�l�́A�Q���ɂ킽���ď���ł��ƐłƂȂ�܂��i�A��������Ԃ̉ېŔ����A����V�ݖ@�l�̋K��ɂ��Ə��ɂȂ�Ȃ��ꍇ������܂��̂ŗ��ӂ��Ă��������j�B
�@�R�D���Z�������R�ɐݒ�ł���F�l���Ǝ҂̏ꍇ��12�����Z�̂R��15���\���Ǝ������Œ肳��Ă��܂����A�@�l�͌��Z�������R�ɐݒ�ł��܂��B
�@�S�D�J�z�������̌J�z�T���̔N����������F�l�͂R�N�ł����A�@�l�̏ꍇ��10�N�i����30�N�S���P���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�̏ꍇ�j�ɂȂ�܂��B
����ʓI�ȃf�����b�g
�@�P�D�@�l�ݗ��̎�ԂƔ�p�F�芼���߂āA�o�L�����Ȃ���Ȃ炸�A�芼�F�؎萔����o�^�Ƌ��ł��K�v�ƂȂ�܂��B
�@�Q�D�Љ�ی��̉����F�l���Ƃł͂S�l�܂ł̌ٗp�ł���ΎЉ�ی��̉����`���͂���܂��A�@�l���肷���1�l�ł��Љ�ی��ւ̉������`���t�����܂��B
�@�R�D�Ԏ��ł��V���~�̖@�l�Z���ł�������F�ϓ����ƌĂ�镔���ŁA�Ԏ��������Ƃ��Ă��ŋ�������܂��B
�����܂萔���ɂ͏o�Ă��Ȃ��u�ΊO�I�ȐM�p�v
�@�ΊO�I�ȐM�p�͂ǂ����Ă��l���Ƃ����@�l�̕���������̂ł��B�Z�������Ō���肵�Ȃ��悤�ɖ@�l���������A�Ƃ����̂����h�ȗ��R�ł��B
�@�F�X�Ȏ��_����@�l��������邩���Ȃ����f���������ǂ��ł��傤�B

�@�e�푊���葱���ɗ��p���邱�Ƃ��ł���u�@�葊�����ؖ����x�v���A�S���̓o�L���i�@���ǁj�ɂ����āA�Q�O�P�V�N�T���Q�X�����^�p�J�n����Ă���܂��B
�@����܂ŁA�����l�́A��Y�i�s���Y��a�������j�ɌW�鑊���葱���ɍۂ��A�푊���l�����܂�Ă��玀�S����܂ł̌ːЊW�̏��ޓ��ꎮ�����ׂđ����������ŁA�NJ��̈قȂ�o�L����e���Z�@�ւȂǁA�����葱������舵���e�푋�����ƂɁA�������ނ����x����o����K�v������܂����B
�@�@�葊�����ؖ����x�ł́A�o�L���i�@���ǁj�ɌːЊW�̏��ޓ��ꎮ���o���A���킹�đ����W���ꗗ�ɕ\�����}�i�@�葊�����ꗗ�}�j���o����A�o�L�������̈ꗗ�}�ɔF�ؕ���t�����ʂ��������Ō�t����܂��B
�@�����āA���̌�̑����葱���́A�@�葊�����ꗗ�}�̎ʂ��𗘗p���邱�ƂŁA�ːЊW�̏��ޓ��ꎮ�����x����o����K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B�s���Y�̓o�L���`�l�i���L�ҁj�����S�����ꍇ�ɂ́A���L���̈ړ]�̓o�L�i�����o�L�j���K�v�ƂȂ�܂��B
�@�������ŋ߂ł́A�����o�L�������̂܂ܕ��u�����s���Y���������Ă���A���ꂪ���L�ҕs���y�n����Ɩ��ȂǗl�X�ȎЉ���̗v���ƂȂ��Ă���Ƃ̎w�E������܂����B�����ŁA�����葱���ɌW�鑊���l���̕��S�y����A�����o�L�𑣐i���邽�߂ɁA�@�葊�����ؖ����x���V�݂��ꂽ�Ƃ݂��Ă���܂��B
�@�����x�ɂ����Ă͂܂��A�����l���͂��̑㗝�l���A�푊���l�����܂�Ă���S���Ȃ�܂ł̌ːЊW�̏��ޓ����W�߁A���̋L�ڂɊ�Â��푊���l�̎����A�Ō�̏Z���A���N�����y�ю��S�N�������тɑ����l�̎����A�Z���A���N�����y�ё����̏��Ȃǂ��L�ڂ����@�葊�����ꗗ�}���쐬���܂��B�����̏��ނ�Y�t�����\�o�����o�L���́A���e���m�F���A�@�葊�����ꗗ�}��ۊǂ��A�F�ؕ��t���̖@�葊�����ꗗ�}�̎ʂ�����t���܂��B
�@���̌�A�@�葊�����ꗗ�}�̎ʂ��́A�����o�L�̐\���葱�����͂��߁A�푊���l���`�̗a���̕��߂��ȂǁA�l�X�ȑ����葱���ɗ��p����邱�ƂŁA�����葱���ɌW�鑊���l�E�葱���̒S�������o���̕��S�̌y�������҂���Ă���܂��B����̓����ɒ��ڂł��B

�@�Q�O�P�T�N�P�����瑊���ł��ېŋ�������A�����ł̊�b�T���z�́u�R,�O�O�O���~�i�Q�O�P�S�N�P�Q���R�P���ȑO�͂T,�O�O�O���~�j�{�U�O�O���~�i���P,�O�O�O���~�j�~�@�葊���l�̐��v�ŎZ�o����܂��B
�@�{�q�́A���q������P�l�A���q�����Ȃ���Q�l�܂ŁA�����l�Ɋ܂߂��܂��B
�@���̂��߁A�����l�������قǍT���z�������đ����Ŋz���������邽�߁A�x�T�w�𒆐S�ɐߐŖړI�ŗ{�q���g������P�[�X���݂��܂��B
�@���������Ȃ��A�����ł̐ߐł�ړI�Ƃ����{�q���g���L�����ǂ�������ꂽ�i�ׂ̏㍐�R�ŁA�Q�O�P�V�N�P���R�P���ɍō��ّ�O���@��́A�u�ߐł̂��߂̗{�q���g�ł����Ă��A�����ɖ����Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ̏����f�������܂����B
�@���̎��ẮA�Q�O�P�R�N�Ɏ��S�����W�Q�̒j�����A�S���Ȃ�O�N�ɒ��j�̑��q�ł��鑷�Ɨ{�q���g���������Ƃ����[�ƂȂ������̂ŁA���̌��ʁA���j�Ɩ��Q�l�������j���̖@�葊���l�́A���Ƃ̗{�q���g���L���ł���S�l�ƂȂ�܂��B
�j���̎���A���Q�l�́u�{�q���g�͖����v�Ƃ��Ē�i���A��R�̓����ƍق͗L���ƔF�肵�܂������A��R�̓������ق��{�q���g���Ɣ��f�������Ƃ���A�������㍐���܂����B
�@��R�̓������ق́A���j������ɘA��Ă����ŗ��m���瑷��{�q�ɂ����ꍇ�̐ߐŃ����b�g�����邱�Ƃe�ɐ������Ă������Ƃ���u�����ő��S�ŁA�j���ɑ��Ƃ̐^���̐e�q�W��n�݂���ӎv�͂Ȃ������v�Ƃ��āA�{�q���g���Ɣ��f���܂����B
�@���̗{�q���g�́A�����ł̐ߐł̂��߂ɂ��ꂽ���̂Ƃ��������ŁA���@�W�O�Q���P���́u�����ҊԂɉ��g������ӎv���Ȃ��Ƃ��v�ɓ�����Ƃ��܂����B
�@����ɑ��A�ō��ق̑�O���@��́A�u�����ł̐ߐł̓��@�Ɖ��g������ӎv�Ƃ͕���������v�Ƃ��������ŁA�u�ߐł̂��߂ɗ{�q���g������ꍇ�ł����Ă��A�����Ɂw�����ҊԂɉ��g������ӎv���Ȃ��Ƃ��x�ɓ�����Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B
�@�{���̗{�q���g�ɂ��āA���g������ӎv���Ȃ����Ƃ��������킹�鎖��͂Ȃ��A�u�j���ɉ��g������ӎv���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ��āA���Ƃ̗{�q���g�͗L���Ɣ������܂����B
�@����̓����ɒ��ڂł��B

���������y�n�̂����A�����Ƃ��Ďg���Ă��镔���̍��Y�]�����߂����Ĕ[�Ŏ҂Ǝ����̂������Ă����ٔ��ŁA�ō��ق͎����̑��̎咣��S�ʓI�ɔF�߂Ă������ٔ�����j�����A����Ȃ錟���𖽂���R�������߂��̔����������܂����B�����ƔF�肳���ΐŕ��S�͂V�`10�����ƂȂ邽�߁A�ٔ��̌��ʂ͕s���Y�����ɑ傫���e���������ł��B
�@�������Y�̕]�����@���K�肵�����Y�]����{�ʒB�ł́A�����Ƃ��ė��p����Ă����n���u�������p��n�v�Ƃ��āA
�@�@�@�s���~�܂�̐������H�ȂǁA����̐l�Ԃ��ʍs������̂ɂ��Ă͕]�����V�����A
�@�@�A�ʂ蔲�����H�̂悤�ɕs���葽���̐l�Ԃ��ʍs������̂ɂ��Ă͂O�~�\�\
�@�ŕ]������ƒ�߂Ă��܂��B
�@�����͑����ł̐\���ɓ������āA�܂��A�̃[���]�������Ƃ��Đ\�������o���܂������A���̌�@�̂V�����������ƏC�����Đ\�����������܂����B�������Ŗ����́u�A�p�[�g�̕~�n�̈ꕔ�ł���A�������������ł͂Ȃ��w�݉ƌ��t�n�x�ł���v�Ƃ��Č��z����̓K�p��F�߂��A�X������������B�s���Ƃ����������i�����N���������̂ł��B
�@�n�فA���ق̔����ł͂Ƃ��Ɏ����̑��̑i�����F�߂��A�[�Ŏ҂��s��܂����B�������ō��قł́A�����̔��f���܂����B�����ɓ����邩�ǂ����́u���z��@�Ȃǂ̖@�߂̐���̗L�������ł͂Ȃ��v�Ƃ��āA�u��n�̈ʒu�W��`��A���H�Ƃ��Ă̗��p�Ȃǂ܂��āA�����I�ɁA�ق��̗p�r�ɓ]�����邱�Ƃ���������l����ׂ��v�Ƃ̔��f�������܂����B


dummy
�@�l�ېłɂ������ȉ������ڂ́A���̂Ƃ���ł��B
������������̐Ŋz�T���̊g�[
�@�����ł́A�Ŋz�T���z�́A�O�N����̎���������̑��z���傫���قǐŊz�T�������傫���Ȃ��Ă��܂��B������Ƃ̏ꍇ�́A�Ŋz�T��������p��12�����Ƃ���Ă��܂������A�����ł�12���`17�����̍T�����ƂȂ��Ă��܂��B
�@����A���Ƃ́A8���`10�����������Ŋz�T������6���`14�����ɉ�������Ă��܂��B
�@�܂��A����������͈̔͂ɂ́A�u�T�[�r�X�̊J���v���ΏۂɂȂ��Ă��܂��B
�������g�呣�i�Ő��̊g�[
�@��ƋK�͂ɂ�����炸�A���^�x�����z���O�N������Ȃǂ̏���̗v���������ƂŁA���グ���z��10���������Łi�@�l�ł���T���j���Ă��܂������A����w�̒��グ�𑣂��ϓ_����A�����ł́A������Ƃ̏ꍇ�A�O�N�ɔ�ׂ�2���ȏ�̒��グ�����{�����ꍇ�ɂ�22�����̐Ŋz�T���A����A���Ƃł��A�O�N�Δ�2���ȏ�̒��グ�����{�����ꍇ�ɂ�10������12�����Ɗg�[���Ă��܂��B�����A���グ��2���ɖ����Ȃ����Ƃ́A���s10�����̐Ŋz�T�������܂���B
���g�D�ĕҐŐ��̌�����
�@���s�Ő��ł́A�X�s���I�t�i����̎��Ƃ�q��Ђ���ƃO���[�v�����o���ēƗ�������ЂƂ���j�ɍۂ��āA�@�@�l�T�C�h�ɂ����Ắu���n���v�i�ړ]���Y���͎q��Њ����j�ېŁv�A�A�l�T�C�h�ł́u�z���i�݂Ȃ��z���܂ށj�ېŁv���������邱�Ƃ���A�V�����Y�Ƃւ̋@���I�Ȏ��ƍĕ҂��ł��܂���ł����B
�@�����ŁA����̉����ł́A�����A�������z�ɂ������āA�����@�l���͌������z�@�l�̊���̎������ɉ����āA���ꂼ��A�������p�@�l�̊������͎q��Њ����݂̂���t�����ꍇ�A���̑�����̗v�������ΉېŊW�������Ȃ��悤�ɂ��܂����B
�@�ȏ�̉����́A����29�N4��1���J�n���ƔN�x����̓K�p�ł��B
��������Ƃ̌y���ŗ��Ɋւ���
�@�N800���~�ȉ��̏������z�̐ŗ��i�{��19���A�d��15���j��2�N�ԉ����ł��B
�@�Ȃ��A������Ƃł����Ă��A���Ϗ������z�i3�N�ԁj���N15���~���鎖�ƔN�x�̓K�p�͒�~����Ƃ��Ă��܂��B
�@���̉����́A����31�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x����̓K�p�ł��B
���������^���ɂ��Č�����
�i�P�j���v�A�����^�ɂ��āA�����Ăł͌��s�̗��v�w�W�Ɋ������̎w�W�i�ƐјA���w�W�j��lj��A�܂��A�v�����Ԃ��P�N�x�w�W���畡���N�x�w�W�Ɋg�債�Ă��܂��B
�@������āA�ƐјA���w�W�Ɋ�Â����̊������̌�t�����^�ɉ����Ă��܂��B
�i�Q�j�ސE���^�ŗ��v���̎w�W����b�Ƃ��ĎZ�肳�����̂̂������̗v�������Ȃ����̂́A���̑S�z���s�Z���Ƃ��A����ɂ��킹�āA���v�A�����^�ɂ��āA�w�W�̑Ώۂ������N�ɂȂ邱�Ƃ��A�ƐіڕW�̒B���x�����ɉ������V���\�̈�萔�̌�t�����^�ɉ����Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�����Z���̎葱�Ɋւ��ẮA���̎����Ɋm�肵�����K���͊���������t���鋋�^�́A���O�m��̓͏o���K�v�B����A�����N�̊��ԂɘA���������K�A����������t���鋋�^�́A��V�ψ���̌����L���،����ł̊J�������K�v�ł��B
�i�R�j���n�����t�������ɂ��āA�����Ăł́A���S�q��ЈȊO�̎q��Ж������t�^�̑Ώۂɉ����Ă��܂��B�܂��A�Z�҂ł�������ɂ��Ă������Z�����Ƃ��Ă��܂��B
�i�S�j������z���^�͈̔͂ɂ��āA�����Ăł́A�ŋy�юЉ�ی����̌������̌�̋��z�������z�͈̔͂ɉ����A�_��ȑΉ��ɉ��߂Ă��܂��B
�@��L�����̓K�p�́A�ސE���^�A���n�����t�����y�ѐV���\�ɌW�镔���͕���29�N10��1���Ȍ�A���̑��̕����͓��N�S��1���Ȍ�Ɏx�����͌�t�̌��c�i���̌��c���Ȃ��ꍇ�A���̎x�����͌�t�j�����鋋�^����ł��B
�����j��ƌ����������i�Ő��̑n��
�@���Ǝ傪�n�撆�j���ƌv��i���́j������i�s���{���̔F��v�j���A������i����L���邱�Ɓi���̔F��v�j�������ɁA�@�B�y�є��i�����擾�����ꍇ�A���ʏ��p40���i�Ŋz�T��4���j�A�������ł�20���i�Ŋz�T��2���j�̓���[�u���V�݂���Ă��܂��B
��������Ɠ������i�Ő���悹�[�u
�@���Y������ݔ����ɌW�鑦�����p���ɂ��ẮA������ƌo�c�����Ő��Ɖ��g���A�o�c�͌���v��̔F��������ɁA�Ώېݔ����g�[���A���̊����i�y�ь����t���ݔ����lj�����Ă��܂��B
�@�K�p�����́A����29�N4��1�����畽��31�N3��31���܂łł��B


dummy
���Y�ېł̎�ȉ����́A���̒ʂ�ł��B
�����Y�]���̓K����
�P�D�������̂Ȃ������]���̌�����
�@�ގ��Ǝ�䏀�����ɂ�銔���̎Z�o���@�ɂ��āA
�i�C�j�ގ��Ǝ�̏���Ђ̊����ɂ��ẮA2�N�Ԃ̕��ς�I���\�ɁA
�i���j�䏀�v�f�ł���A�z�����z�A���v���z�y�ѕ뉿�����Y���z�ɘA�����Z�f�������̂Ƃ���A
�i�n�j�䏀�v�f�̃E�G�C�g���u�P�F�P�F�P�v�i���s�P�F�R�F�P�j�ɁA
�i�j�j��ЋK�͂̔����ɂ��āA���Ћy�ђ���Ђ̓K�p�͈͂𑍂��Ċg�傷��B
�A�����ۗL�����Ђ̔����ɁA�V���\�t�Ѝ�������B
�Q�D�L��n�]���̌�����
�@�ʐςɉ����Ĕ��I�Ɍ��z���錻�s�̕]�����@����A�e�y�n�̌��ɉ����ĖʐρE�`��i���s�A�s���`�j���Ɋ�Â��]��������@�Ɍ������A�K�p�v���m������B���̉����́A��L�P�̇@�͕���29�N1��1���Ȍ�A�P�̇A�ƂQ�́A����30�N1��1���Ȍ�ɑ������ɂ��擾�������Y�̕]������̓K�p�ł��B
�������œ��i���^�j�̔[�ŋ`���̌�����
�@�����œ��̔[�ŋ`���͈̔͂ɂ��ẮA�����l�����͔푊���l���̏Z���v����10�N�i���s�F5�N�j�ȓ��ɉ����A�Z�����ꎞ�I�ł���O���l���m�̑������ɂ��ẮA���O���Y���ېőΏۂɂ��Ȃ��A���{�ɏZ���y�э��Ђ�L���Ȃ������l�����A�ߋ�10�N�ȓ��ɓ��{�ɏZ����L���Ă����푊���l�����瑊�����ɂ��擾�������O���Y�͉ېőΏۂƂ���i�Z���؍݂̊O���l�������j�B���̉����́A����29�N4��1���Ȍ�̑���������̓K�p�ł��B
����Ö@�l�̎��������Ƒ��^�ې�
�@���������Ö@�l�������Ȃ���Ö@�l�ւ̈ڍs�v��̔F����A���̗v�����[�������ꍇ�A���Y��Ö@�l�̎��������ɔ����o�ϓI���v�ɂ͑��^�ł��ۂ��Ȃ��A�Ƃ���������Ȃ���Ă��܂��B�K�p�ɂ��ẮA���v�̑[�u���u������ƂȂ��Ă��܂��B
���^���}���ېł̌�����
�@���Z�p�����w���z���i�^���}���j�ɉۂ��Œ莑�Y�łɂ��ẮA�K�w�ʐ�L���ʐϕ���i1�K��100�Ƃ��ĊK���P�������Ƃ�39����10�����������l�j��K�p�����ېłɉ��߂��܂��B�����́A����30�N�x�i����29�N4��1���O�ɔ����_�������ꂽ���̂������j����V���ɉېł������̂ɓK�p����܂��B

����28�N12��8���A����29�N�x�Ő�������j�����\����܂����B�悸�A�u�l�����ېŁv�ɂ��āA��ȉ������ڂɂ��A���e���T�ς��Ă݂܂��B
���z��ҍT�����̌�����
�@�z��ҍT���ɂ��ẮA���v�������z1,000���~���鋏�Z�҂ɂ��ẮA�K�p�ł��Ȃ����ƂƂ��A���Z�҂̍��v�������z��900���~�����38���~�i�V�l�z���48���~�j�̍T���z�����X�ɏk�����A1,000���~���ł̓[���ɂȂ�A3�i�K�Œ�������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�@�܂��A�z��ғ��ʍT���ł����A�z��҂̍��v�������z��38���~��123���~�ȉ��ł�9�i�K�Œ������Ȃ���T�������܂����A��L�̋��Z�҂̍��v�������z�ɉ����čT���z���ς���Ă��܂��B
�@�Ⴆ�A���Z�҂̍��v�������z900���~�ȉ��Ŕz��҂̍��v�������z��95���~��100���~�ȉ��ł����26���~�̍T���A�ƂȂ��Ă��܂��B���̉����́A����30�N���Ȍ�̏����ł���̓K�p�ƂȂ��Ă��܂��B
���ϗ��^�̏��z�����m�h�r�`�̑n��
�@���x�̓��e�́A�ϗ��������x�z�N��40���~�A����20�N�A���̊Ԃ̔z���A���n���͔�ېŁA
�@�A���A���n���͂Ȃ����̂Ƃ���B���s�̂m�h�r�`�Ƃ͑I��K�p�ƂȂ��Ă��܂��B
�@��L�����́A����31�N���Ȍ�̏����ł���̓K�p�ƂȂ��Ă��܂��B
�����t�H�[�����ł̊g�[
�@�����Z��i����̑����z���܂ށj�̑ϐk���C�E�ȃG�l���C�ɉ����A���̑ϋv��������C�H�������{�����ꍇ�A���[���̗��p�ɂ�錸�Ŋz�i�Ŋz�T���j�͍ő�62.5���~�A���Ȃ̎����ɂ��ꍇ�͍ő�50���~�ƂȂ�[�u���u�����Ă��܂��B
�@�܂��A�Œ莑�Y�Łi�H�����N�x�j��3����2���z�ɂȂ�܂��B���̑ϋv��������C�H���Ƃ́A50���~����H���ŁA
�@�@�������A�A�O�ǁA�B�����A�E�ߎ��A�C�y��A���g���A�D�����A�E��b�Ⴕ���͇F�n�ՂɊւ����H�����͋��r���Ǔ��Ɋւ���ێ��Ǘ��E�X�V��e�Ղɂ��邽�߂̍H���ŁA�F����������D�ǏZ��z���v��Ɋ�Â����̂ł��邱�Ɠ��A�ł��B
�@���̉����́A�����z�����������Z�p�Ɖ���29�N4��1�����畽��33�N12��31���܂ł̊ԂɎ��Ȃ̋��Z�p�ɋ������ꍇ�ɓK�p�ƂȂ��Ă��܂��B
�Ј��̋������A�b�v������Ƃ̖@�l�ŕ��S���y������u�����g�呣�i�Ő��v�ɂ��āA������Ƃ��Q���ȏ���グ�����Ƃ��͍ő匸�Ŋz��22���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ肻���ł��B���͌��ŕ��̊g��Œ�����Ƃ̒��グ�𑣂��_���ł��B
�@���s���x�ł́A
�@�@�@���^�x�����z������24�N�x����R������
�@�@�A���^�x�����z���O�N�x�ȏ�
�@�@�B�]�ƈ��P�l������̕��ϋ��^���O�N�x�ȏ�
�\�\�̂R�v��������Ƃ́A���グ���z��10����@�l�Ŋz����Ŋz�T���i������Ƃ͐Ŋz�̍ő�20���A���Ƃ�10���j�ł��܂��B�F�\�������Ă���l���Ǝ傩����Ƃ܂ŕ��L�����p�ł��鐧�x�ł��B�����ł����u���^�v�́A�����Ŗ@��u���^�����v�Ƃ��ĉېł����ܗ^�⏔�蓖���܂݂܂��B
�@���ꂪ�Ő������ɂ��A�������O�N�x��Q���ȏ�̏�������������Ƃ�ΏۂɁA���グ���z�̍ő�22����@�l�Ŋz���獷���������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�ϋɓI�ɒ��グ�Ɏ��g�ޒ�����Ƃ̐ł̌y�����ʂ�傫�����邱�ƂŁA���ƕ��݂̒��グ�ɂȂ���悤�ɂ���Ƃ̂��Ƃł��B
�����F�G�k�s�[�ʐM�Ё�
���{�͕���29�N�x�Ő�������j�ɁA���w�}���V�����̏�w�K�̌Œ莑�Y�Ŋz�����グ�荞�ޕ��j���ł߂܂����B�Œ莑�Y�ŕ]���z�Ǝ������i�̊J���𗘗p�����u�^���}���ߐŁv�ɁA�Ƃ��Ƃ��ېŋ����̖Ԃ��������邱�ƂƂȂ�܂��B
�@�}���V�����̌Œ莑�Y�łɂ́u�K�w�v�Ƃ����T�O�͂Ȃ��A�P�K�ł��낤��50�K�ł��낤�ƁA�����ʐςɂ͓����Ŋz���������Ă��܂��B�������Ă���V���Ȍv�Z���@�́A���w�K�قǏd���S�ɁA��w�K�قnjy���S�ɂ���Ƃ������́B�����悻20�K�����E���Ƃ��A�������̊K�ł���ΌŒ莑�Y�]���z�����݂�荂���Ȃ邻���ł��B��̓I�ȎZ����@�Ȃǂ͍���l�߂邽�߁A�ǂ̊K�w����ǂ̒��x�ŕ��S��������̂��͖��m��B���{�͔N���܂łɍ��i���ł߂ĐŐ�������j�ɐ��荞�݁A������ė��N����V���x���J�n������j���Ƃ��Ă��܂��B
�@����̉����̖ړI�́u�������i�ƌŒ莑�Y�ŕ]���z�̃M���b�v�v�̉����ł��B50�K�ȏ゠��悤�ȃ^���[�}���V�����ł́A��w�K�Ƃ̉��i�����P���~�ȏ�J�����Ƃ��������Ȃ����߁A���Y���l�ɍ�������̂ɌŒ莑�Y�ł�����Ȃ͕̂s�������Ƃ��������������Ă���Ƃ����̂��A�^�}�̐������錩�����̗��R�ł��B
�@����ɁA�ߔN�x�T�w�̊Ԃōs���Ă��������ő�̎�@�ł���u�^���}���ߐŁv���_����������邱�ƂɂȂ�܂��B�s���Y�𑊑����Y�Ƃ��ĕ]������ۂɂ́A�Œ莑�Y�ŕ]���z���Z���b�Ƃ��ėp�����܂��B�܂�K����J�h�����Ƃ������v�f�͍l������܂���B��q�����悤�ɁA�}���V�����̕������̌Œ莑�Y�ŕ]���z�͊K���ɂ�����炸����B����ɑ��A���ۂ̎�����i�͍��w�K�قǍ����Ȃ�X��������܂��B�^���}���ߐł͂��̍��𗘗p���āA�����ŕ��S��}����X�L�[���ł��B
�����F�G�k�s�[�ʐM�Ё�
���w�E�̑����̂��Q�����Z
�@�����ł̊�b�T�����������ɂ��A�ېőΏێ҂��啝�ɑ������A���Œ��ł͐\�����̓��e�Ɍ�肪����Ƌ^����ꍇ�ɁA�[�Ŏ҂ɕ����𑗕t���\�����̌������𑣂��Ă��܂����A���Ɏw�E�̑����̂��u�����Ŋz�̂Q�����Z�v�̂悤�ł��B
�������Ŋz�̂Q�����Z
�@�u�����Ŋz�̂Q�����Z�v�Ƃ́A�������͈②�ɂ����Y���擾�����҂��A�푊���l�̈�e���̌����y�єz��ҁA�ȊO�̎҂ł���ꍇ�ɁA�����Ŋz���Q�����Z����Ƃ�����̂ł��B��e���̌����Ƃ͕����q���w���܂��B���̂��߁A����ȊO�̎ҁA���Ȃ킿�A�푊���l�̌Z��o�����������ō��Y���擾�����ꍇ��A�����W���Ȃ��҂ȂǂɈ②���������ꍇ���ɂQ�����Z������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�܂��A�����Q�����Z�̑Ώۂł����A�푊���l�̎q�������J�n�ȑO�Ɏ��S����Ȃǂ��A��P�����l�ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ͂Q�����Z�͕s�v�ł��B
����e���̖@�茌���ł����{�q�́c
�@��e���̌����ɂ́u�{�q�v���܂܂�܂����A��O������A�푊���l�̒��n�ڑ��Ŕ푊���l�̗{�q�ɂȂ��Ă���ҁA�܂�g���{�q�h�͂Q�����Z�ΏۊO�Ɋ܂܂�܂���i��P�����l�͏����j�B�u�{�q�v�ɂQ�����Z�͂Ȃ����A�g���{�q�h�Ɍ����Ă͂Q�����Z������Ƃ������̎戵���̂Ƃ���ɊԈႢ�������悤�ł��B
�����{�q�ގ��̈�e���̖@�茌�������c
�@���Œ��̎��^��������Ɂu�푊���l�̒��n�ڑ��łȂ��҂��{�q�ƂȂ��Ă���ꍇ�v�̎��Ⴊ����A�����ł́u�q�̔z��ҁv���{�q�ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂQ�����Z���Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B���Ȃ킿�A�g���{�q�h�ȊO�́u�{�q�v�͈�e���̌����Ɋ܂܂�邽�߁A�Ⴆ�A�u���̔z��ҁv��u�{�q�̗{�q���g�O�̎q�i�{�q�̘A��q�j�v���{�q�ƂȂ��Ă��Ă��Q�����Z�͕s�v�ł��B
����P�����ł��Q�����Z������
�@���Œ��̎��^��������ɂ́A��P������������Б��ŁA�②������̂ő�P�����l�̒n�ʂ���������ꍇ�A���̑��������҂ɂ͂Q�����Z���O�̓K�p���Ȃ��A�Ƃ�����������Љ�Ă��܂��B�i��P�����̋K��ł͕������Ȃ��������̂Ƃ���Ƃ��Ă��Ȃ��B�j
�@�l�ŕs���Y�̒��Ƃ��c�ޕ��i�ƐŎ��Ǝҁj���A���܂��ܑO�X�N�̕���26�N�i�{�N�A����28�N�j�A���������Ԃɒ��ݗp������1�疜�~���i�ō��j�ŏ��n���Ă����ꍇ�A�{�N�A����28�N�͉ېŎ��Ǝ҂ɂȂ��āA���ɁA�{�N���ɑݓX�ܓ��̒��ݎ����Ȃǂ�����Ώ���ł̔[�ŋ`���������邱�ƂɂȂ�܂��B
���ƐŎ��Ǝ҂ɂƂ��Ă͗\�����
�@�Ƃ����̂��A�l�ŏ��K�͖��͋��Z�p�s���Y�̒��Ƃ��c��ł�����́A���n�N�i�O�X�N�j�ɂ����Ă��A�����̏ꍇ�͖ƐŎ��Ǝ҂ł��������ł̔[�ŋ`���͐����܂���B�܂��A���Ǝ҂̕����g���ېł��Ɛł�����i�ӎ�����Ă��Ȃ����Ƃ������Ă��A���n�������N�̗��X�N�̏��C�ɗ��߂邱�Ƃ͂܂��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@���̂悤�ȃP�[�X�ŁA����28�N�ɍēx�A�ʂ̒��ݗp���������n���Ă��܂����Ƃ�����܂��B���̏Ɏ����ẮA�Г�Ƃ������鍓�ȏ����������܂��B�����̏��n���z��5�疜�~�ł���A�P���Ɍ��ς����āA����Ŋz�̕��S��400���~�����ł��B����ŕ��S�z�̗\���\����F������ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A�O�X�N�̏��n���ɐł̐��Ƃ̊֗^���s�����Ǝv���܂��B
���ȈՉېł̑I���ƉېŊ��Ԃ̒Z�k
�@����27�N���ɊȈՉېőI���̓͏o�����O�A�����āA�{�N�̔����_���������n�O�̒i�K�ŁA�ǂ̂悤�Ȑŕ��S�y���̑u�����邩�ł����A�ȉ������E�̂悤�Ɏv���܂��B�����Ƃ��A�O�X�N�̉ېŔ��㍂5,000���~�i�ō��j�ȉ����O��ł��B
�@�@3�����Ԃ̉ېŊ��Ԃ̒Z�k�ƊȈՉېőI���̓͏o���̒�o�A
�@�A3�����Ԃ̉ېŊ��Ԃ̒Z�k�̓͏o���Ԃɍ���Ȃ���A1�����Ԃ̉ېŊ��Ԃ̒Z�k��
�@�@�ȈՉېőI���̓͏o���̒�o�ł��B
�@�������A�����ېŊ��Ԃ̒Z�k�ƊȈՉېł�I������Ƃ��̓K�p��2�N�Ԍp�����邱�ƂɂȂ�܂����A�������n�ɔ����ېŊ��Ԃ̏���ł̕��S���y���ł���A�ƐŎ��Ǝ҂ɂ����ẮA���̌�̉ېŊ��Ԃ͔�ېŔ��オ���|�I�ɑ����A�ېŔ��オ�����Ă��͂��ł��̂ő傫�Ȏ������S�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA���ݗp�����̏��n�ɔ����ȈՉېł݂̂Ȃ��d���ꗦ��40���ł͂Ȃ�60���ł��B���Ȃ��Ƃ��A����ł̕��S�𑊓��y���ł��܂��B
���u��N���^�T�|�[�g�T�[�r�X�v�̏Ɖ��
�@���Œ��̃z�[���y�[�W�ɂ́A�u���O�Ɖ�ɑ��镶������v�����\����Ă��܂����A����28�N3���ɋC�ɂȂ�Ɖ�Ⴊ�f�ڂ���܂����B������Z�@�ւ��Ɖ���u��N���^�T�|�[�g�T�[�r�X�𗘗p�����ꍇ�̑����Ŗ@��24���̊Y�����ɂ��āv�Ƃ������̂ł��i�������ŋljj�B
�@���́u��N���^�T�|�[�g�T�[�r�X�v�Ƃ́A���̋��Z�@�ւ̗a��������L����3�e���ȓ��̐e���W�ɂ��镡���̌l��ΏۂƂ��āA���̌l�Ԃ́u���^�̈ӎv�y�ё��^���z�̊m�F�v���s���A�u�o�����ӂ�������ꍇ�v�Ɍ���A�u���^�_�̍쐬�v��u�a���̐U�ցv�����T�|�[�g����T�[�r�X�Ȃ̂������ł��B���̃T�[�r�X�Ɋ�Â����^�́A�����Ŗ@�́u��������t�_��Ɋւ��錠���v�ɊY������̂��Ƃ����̂��Ɖ�̓��e�ł����B
���u��������t�_��Ɋւ��錠���v�Ƃ�
�@�u��������t�_��Ɋւ��錠���v�Ƃ͕�������Ȃ����t�ł����A������u�N�����v���w���܂��B���Ƃ��A�`���a�ɑ���5�N�Ԍ���100���~�����^����ꍇ�A������u����1�N���ƂɌʂ�100���~�����^����v�ƌ��邱�Ƃ��ł���A�e�N��110���~�̊�b�T�����K�p�ł��܂��̂ŁA���^�ł͉ېł���܂���B�����A�������5�N�ԁi���N�j����100���~���^�������ł���Ȃ�A�����5�N���́u������i�N���j�����錠���v���擾�����ƔF�肳��A�ꎞ�ɑ��^�ł��ېł���鋰�ꂪ����܂��B���̏ꍇ�ɁA���^�������̂Ƃ݂Ȃ������z�́A���̇@�`�B�̂����ꂩ�������z�Ƃ���Ă��܂��B
�i�L��������̏ꍇ�j
�@�@�@�@���Ԗߋ��̊z
�@�@�A�@�@�ɑウ�Ĉꎞ�����邱�Ƃ��ł���ꍇ�c�ꎞ��
�@�@�B�@1�N�ԂŎ�ׂ����z�~�c�����Ԃɉ�����\�藘���̕����N��������
���u�����v�ɂ͒�������t�_��ƔF�肹��
�@���̂��߁A�����́u�A�N���^�v���s���ꍇ�Ɠ��l�ɁA���̃T�[�r�X���u��������t�_��Ɋւ��錠���v�ɓ�����]�n�����邩�S�z���c�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�������ŋǂ̉́A���̃T�[�r�X��p�����ꍇ�ɂ́A���^�̓s�x�̊m�F�����邽�߁A�u�����Ɂv�͒�������t�_��Ƃ͔F�肵�Ȃ��Ƃ̂��Ƃ̂悤�ł��i�_��̓��e��ʂ̏ȂǂŔ��f����]�n�͂���̂ł��傤���ˁc�j�B
���N�X������⌾�쐬����
�@�����E�⌾�ɑ���S�͔N�X���܂��Ă���A����26�N1���`12���ɑS���̌��ؖ���ō쐬���ꂽ�⌾�i�����؏��⌾�j��10�N�O�����4�������������A����10�������܂����B�ƒ�ٔ����ň���ꂽ��Y�������������l�ɑ����X���ɂ���A���������w�i���e�����Ă��邱�Ƃ����������܂��B�̐l�̈�u���ł��邩���葸�d���������̂ł����A�⌾���������Ƃ��Ƒ������ł͉Ƒ��̏��ς���Ă��܂��Ƃ������Ƃ�����܂��B�ł́A�⌾�̓��e�ƈقȂ��Y�̕��������邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��傤���B
���⌾�ƈႤ��Y�����͉\�H
�@�����l�̊Ԃň�Y�����̕��@��b���������Ƃ���Y�������c�ƌ����A���̌��ʂ����ʂɂ������̂���Y�������c���ł��B
�@����ł́A
�@�@�⌾�ɂ���Ĉ�Y�������c���֎~����Ă���ꍇ
�@�A�⌾���s�҂��I�C����Ă���ꍇ
�@�������A�⌾�ƈقȂ���e�̈�Y�������c�����邱�Ƃ͎�����F�߂��Ă��܂��B���ہA�⌾�ƈقȂ��Y�����̕��@�����c���邱�Ƃ͒���������܂���B
�@�������A������ƌ����đS�Ĉ�Y�������c�����⌾�ɗD�悷��A�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�⌾�̓��e�ɂ���Ă͒��ӂ��K�v�ł��B
����Y�����̕��@���w�肳�ꂽ�⌾
�@�ߋ��A�ō��قł́A����̍��Y�����̑����l�ɑ�����������e�̈⌾�̏ꍇ�A�⌾�҂̎��S�ɂ���āA���Y�͒����Ɋm��I�ɑ����l�ɋA������Ƃ����������s���܂����i����3�N4��19���ō��ٔ����j�B�u����̍��Y�����̐l�ɑ�����������e�v�Ƃ́A���Ƃ��u���j�����ɍ�ʌ��~�~�̓y�n�𑊑�������v�Ƃ����̂�����ɂ�����܂��B���̏ꍇ�A���̌�ɍs������Y�����͖{���̈Ӗ��ł́u��Y�����v�ł͂Ȃ��A�����l�Ԃ̎���Ƃ��č��Y���ړ]������̂Ƃ���Ă��܂��B
���̌��ʁA�s���Y�̑����o�L���s���ہA��Y�������c�̌��ʂ��������ܓo�L�ł����A�܂��́u�⌾�Ɋ�Â��o�L�v��������A�u�����l�Ԃ̎���̓o�L�v�̓�i�K�Ő\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǁA���������Ɏx������������Ƃ�����܂��B�����Ȃ�Ǝ葱����p����Ԃ���d�ɂ������Ă��܂��܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
�Q�O�P�U�N�x�Ő������ɂ����āA�ٗp�𑝂₷��Ƃ����ł���ٗp���i�Ő��́A�K�p�ΏۂƂȂ�ٗp�҂��t���^�C���̋Ζ��҂Ɍ��肵�A�܂��A�Ώےn���啝�ɏk��������œK�p�������Q�N��������܂��B
�@�Ώےn�悩��A���Ő��̑O��ƂȂ�ٗp���i�v����n���[���[�N���t���������̏�ʂł��铌����_�ސ�A���A���m�Ȃǂ͏��O����A�Q�W���{���A�n���[���[�N�̊NJ����ł͂P�O�P�n��ɏk������܂��B
�@�����ɂ��A�ٗp�҂̐������������ꍇ�̓��ʐŊz�T�����x�i�ٗp���i�Ő��j�ɂ�����n�����_�����Ő��ȊO�̑[�u�ɂ��āA�K�p�̊�b�ƂȂ鑝���ٗp�Ґ���n��ٗp�J�����i�@�̓��ӌٗp�J�����i�n����ɂ��鎖�Ə��ɂ����閳���ٗp���t���^�C���̌ٗp�҂̑������i�V�K�ٗp�Ɍ�����̂Ƃ��A���̎��Ə��̑����ٗp�Ґ��y�і@�l�S�̂̑����ٗp�Ґ�������Ƃ���j�Ƃ�����A���̓K�p�������Q�N�������܂��B
�@�ΏۂƂȂ�ٗp�҂́A����܂Ōٗp�ی��̈�ʔ�ی��҂ɊY������p�[�g��A���o�C�g���ΏۂƂȂ�܂������A������͖����ٗp���t���^�C���̌ٗp�҂ŐV�K�ٗp�Ɍ��肳��܂��B
�@���̌��ʁA�Ŋz�T���z�̌v�Z�́A���s�́u���������ٗp�ی���ʔ�ی��҂̐��~�S�O���~�v����A������́u���ӌٗp�J�����i�n����̎��Ə��ɂ�����V�K�����̖����ٗp���t���^�C���̈�ʔ�ی��҂̐��~�S�O���~�v�ƂȂ�܂��B
�@�u���ӌٗp�J�����i�n��v�Ƃ́A�ŋ߂R�N�Ԗ��͂P�N�Ԃ̃n���[���[�N�ɂ����鋁�E�҂ɑ��鋁�l���̊����i��p�L�����l�{���j���S�����ς̂R���̂Q�ȉ��Ȃǂ̗v���ɓ��Ă͂܂�n��ŁA�n���[���[�N�̊NJ����łP�O�P�n��A�Q�W���{�����Y�����܂��B
�@�ٗp���i�Ő��̑O��ł���ٗp���i�v��̂Q�O�P�T�N�x��t�ɂ��܂��ƁA�Q���W,�V�X�S���̂����A�����s�i�U,�R�X�W���j��A���{�i�R,�R�W�T���j�A���m���i�Q,�W�P�T���j�Ȃǂ͑ΏۊO�ƂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A���̉����ɔ����A�ٗp���i�Ő��̓K�p�̊�b�ƂȂ�u�ٗp�ҋ��^���x�������z�v����u�����ٗp�҂ɑ��鋋�^���x���z�Ƃ��Ĉ��̕��@�ɂ��v�Z�������z�v���T��������ŁA�����g�呣�i�Ő��ƌٗp���i�Ő����d�����ēK�p���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��̂ŁA�Y������܂����́A���m�F���������B
������:��L�̋L�ړ��e�́A�����Q�W�N�T���X�����݂̏��Ɋ�Â��ċL�ڂ��Ă���܂��B
�@����̓����ɂ���ẮA�Ő��A�W�@�ߓ��A�Ŗ��̎戵�������ς��\�����\������܂��̂ŁA�L�ڂ̓��e�E���l���͏����ɂ킽���ĕۏ������̂ł͂���܂���B
�l�ېłɂ��ẮA�z��ҍT�����e��T���̔��{�I�ȉ����͌������܂����B�ȉ��A��ȉ������ڂ��T�ς��Ă����܂��B
���ƂɌW����n�����̓���
�����A�s���Y�́A���̈�Y�ƂȂ邱�Ƃ�����A�Ƃ��Љ��艻���Ă��܂����B���̉������̓���̑n�݂ł��B����̓��e�́A���̂Ƃ���ł��B
����������3�N���o�߂�����ɑ�����N��12��31���܂łɁA�푊���l���Z��ł����Ɖ��𑊑����������l���A���Y�Ɖ��i�ϐk��������������̂Ɍ���A���̕~�n���܂ށj���͏�����̓y�n�����n�����ꍇ�ɂ́A���Y�Ɖ����͏�����̓y�n�̏��n�v����3,000���~���T�����邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������̂ł��B
�A���A����̗v�����N���A�[���Ȃ���Ȃ�܂���B�Ⴆ�A
�@�@�@�Ɖ��́A���a56�N5��31���ȑO�Ɍ��z���ꂽ�Ɖ��i�}���V�����������j�ł����āA
�@�@�@�����������ɁA�푊���l�ȊO�̋��Z�҂����Ȃ����ƁB
�@�@�A������������n���_�܂ŁA���Z�A�ݕt���A���Ƃ̗p�ɋ�����Ă��Ȃ����ƁB
�@�@�B���n���z��1���~���Ȃ����ƁA�Ȃǂł��B
�K�p���Ԃ́A����28�N4��1�����畽��31�N12��31���܂ł̊Ԃ̏��n�ł��B
���O���㓯�����C�H���̓���
�O���㓯���̂��߂ɉ��C�H�����s�����ꍇ�A���̇@���͇A�̓��Ⴊ�K�p�ł���K��ŁA�V���ɑn�݂��ꂽ���̂ł��B
�@�@�@���C�H���̏Z��ؓ������i���Ҋ���5�N�ȏ�j�̔N���c��1,000���~�ȉ��̕�����
�@�@�@���āA��芄�����悶�����z��5�N�Ԃ̊e�N�ɂ����ď����Ŋz����T������B
�@�@�A���C�H���̕W���I�Ȕ�p�̊z��10�������z�����̔N���̏����Ŋz����T������B�@
�@
�K�p�Ώۊ��Ԃ́A����28�N4��1�����畽��31�N6��30���܂ł̊Ԃɋ��Z�ɋ������Ƃ��ł��B
���C�H���ɂ͗v��������A���̑ΏۍH���́A�@�L�b�`���A�A�����A�B�g�C���A�C���ւŁA�����āA�@�`�C�̂����ꂩ�݂��邱�ƁA���C��A�@�`�C�̂����A�����ꂩ2�ȏオ�����ɂȂ邱�ƁA�H���50���~���ł��邱�ƂȂǂł��B
�����̑��̉���
�@�@�@�Z�҂ւ̑����ɌW��u���O�]�o�i�����j���ېŁv�Ɋւ���Y����
�@�@�@���c�m��ɂ��C���\����X���̐�����F�߂�B
�@�@�A�s�̖�̈��z�w���ɂ�鏊���T���̑n�݁i��Ô�T���Ƃ̏d���K�p�s�j
�@�@�B�ʋΎ蓖�̔�ېŘg15���~�܂ł̈��グ���ł��B
�����肩��t�Z���ē�d�ېŔr��
�@���ʗa���̎�旘���ɂ͗����x�������������ė��Ȃ��̂ŁA�ʒ��ɋL�ڂ��ꂽ��旘���̋��z����t�Z���āA�������ꂽ�����ł╜�����ʐŁA���q���z�����߂܂��B���̎�旘���̕��������Čv�Z���ꂽ���q���z�́A�@�l�s���{�����ł̐\���ŁA�Ŋz�T������A�T��������Ȃ��z������ꍇ�ɂ͊ҕt����܂��B
�@����́A�@�l�̎�旘�����A�@�l�̉ېŏ����Ɋ܂܂�邱�Ƃ���A��d�ېł�r�����邽�߂̕K�v�Ȏ葱�Ƃ��čs���܂��B
������25�N�Ő������Ő��x�v�̕ύX
�@���̉�v�����Ɛ\���葱�ɕω����N���Ă��܂��B����28�N�P���P���Ȍ�ɖ@�l�̎�旘���ɑ��闘�q���̐��x���p�~���ꂽ����ł��B����25�N�̒n���Ŗ@�̉����ł��B
���[�Ŏҗ��ւ���D��
�@�@�l�s���{�����ł̐\����������ƁA�u���q���ҕt�z�̋ϓ����ւ̏[���v�Ƃ�����������A�[�Ŏ҂��u��]����v�u��]���Ȃ��v��I�����āA�葱�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B10�N�قǑO����݂����Ă�����̂ŁA�[�Ŏ҂ɗ�������邽�߂ɂƉ������Ă��܂��B
�@�{���́A�ېœ��ǂ̎����Ƌ��K���S�̉�����{���ł��B
�@���q���̉ېŒ����́A���q�̎x�����Z�@�֏��ݓs���{���ŁA���R�����ɂȂ�܂��B���q���z�̍T���A�ҕt�́A�@�l�̎傽�鎖�������ݓs���{���ňꊇ�������邽�߁A�s���{���ԂŐ��Z���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�܂��A�V���̖@�l���Ԏ��\���Ƃ����̒��ł́A���q���ҕt�͕��ՓI�ł���A���~���x�̊ҕt�ɐ��S�~�̐U�����S������Ԃɔߖ������Ă����A�Ƃ���ł��B
�����q�����x�n�ݎ��̏Ƃ��̌�
�@���q���̐��x�́A���a62�N�x�Ő������ɂ����đn�݂���A���a63�N�S��������{���ꂽ���̂ł��B�����ɂ����ẮA���Z�@�ւ��l�Ɩ@�l�̌�������ʂ��邱�Ƃ�����Ȃ̂ŁA��ʂȂ��K�p���邱�ƂƂ���܂������A���݂ł́A�y�C�I�t��{�l�m�F�@�A�ƍߎ��v�ړ]�h�~�@�Ȃǂ̐��x�ɑΉ����Ă������ʁA���q�����x����@�l��S�ʓI�ɓK�p���O�Ƃ��邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���A�Ɖ������Ă��܂��B
�@���N�̍����̖@�l�s���{�����Ő\��������́A���q���T���Ƌϓ����ւ̏[���Ƃ̗��͏����Ă���͂��ł��B
����łɂ��ẮA����29�N4��1������y���ŗ����x���A�����āA�Ώەi�ڋy�щېŕ����ɂ��Ă̍��i�����܂�܂����B�ȉ��A���̓��e���T�ς��Ă����܂��B
���y���ŗ��Ώەi�ڋy�ѐŗ�
�i�P�j�Ώەi�ڂ́A�@���H���i�̏��n�i���H�X�c�Ɠ����c�ގ��Ǝ҂��A���̈��H�ݔ��̂���ꏊ���ɂ����čs���H���̒������j�A�A����w�nj_�������ꂽ�T2��ȏ㔭�s�����V���̏��n�A�Ƃ���Ă��܂��B�Ȃ��A���H���i����́A��ނ������Ƃ��Ă��܂��B
�i�Q�j�ŗ��́A8���i�����F6.24���A�n�����F1.76���j�ł��B
���K�i���������ۑ�����
�i�P�j�ېŕ����́A�K�i���������ۑ������A������u�C���{�C�X���x�v�����邱�ƂɌ��肵�܂����B���̕����́A�o�^�����ېŎ��Ǝ҂���t����K�i�������y�ђ���̕ۑ����d���Ŋz�T���̗v���Ƃ�����̂ŁA��̓I�ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@�@�K�i�������ɂ́A
�@�@�@���s�҂̎������͖��̋y�ѓo�^�ԍ�
�@�@�A����N����
�@�@�B������e�i�y���ŗ��Ώۂł���|�̋L�ڂ��܂ށj
�@�@�C�ŗ����Ƃɍ��v�����Ή��̊z�y�ѓK�p�ŗ�
�@�@�D����Ŋz��
�@�@�E��t���鎖�Ǝ҂̎����y�і���
�@�@���L�ڂ���܂��B
�i�Q�j�Ŋz�v�Z�̕��@�́A�K�i�������̐Ŋz�̐Ϗグ�v�Z�ƁA������z����̊��߂��v�Z�̑I���ƂȂ��Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���̓K�i���������ۑ������̐��������́A����33�N4������ƂȂ��Ă��܂��B
�����������܂ł̌o�ߑ[�u
�@����33�N3���܂ł̌o�ߑ[�u�̓��e�́A���̂Ƃ���ł�
�i�P�j���s�̐��������ۑ��������ێ����A�敪�o���ɑΉ�����[�u���u���Ă��܂��B��̓I�ɂ́A�������ɇ@�y���ŗ��̑Ώەi�ڂł���|�ƁA�A�ŗ����Ƃɍ��v�����Ή��̊z���L�ڂ���i�敪�L�ڐ��������ۑ������j�B�����āA��L�A�@�E�A�ɂ��ẮA�敪�L�ڐ������̌�t�������Ǝ҂��A�����Ɋ�Â��NjL���邱�Ƃ�F�߂�A�Ƃ�����̂ł��B
�i�Q�j�Ŋz�v�Z�̕��@�́A���グ���͎d�����ŗ����Ƃɋ敪���邱�Ƃ�����Ȏ��Ǝ҂ɑ��A����Ŋz���͎d���Ŋz�̌v�Z�̓����݂���A�Ƃ�����̂ł��B
������������̌o�ߑ[�u
�@�K�i���������ۑ������̓�����6�N�ԁA�ƐŎ��Ǝ҂���̎d����ɂ��āA��芄���̎d���Ŋz�T����F�߂Ă��܂��B
����28�N�x�Ő������ɂ�����A�@�l�ʼn��v�̊�{���O�́A�u�ېŃx�[�X���g�債�ŗ�������������v�ł���A�f�t���E�p�A�o�ύĐ����ŏd�v�ۑ�Ƃ��Ă��܂��B
�ȉ��A���ł𒆐S�Ɏ�ȉ������ڂ��T�ς��Ă����܂��B
���@�l�ł̐ŗ�������
�@�@�l�ł̐ŗ��́A����28�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ��ẮA23.4���i�W���ŗ��x�[�X�ł̎����ŗ�29.97���j�A����30�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ��ẮA23.2���i�W���ŗ��x�[�X�ł̎����ŗ�29.74���j�Ƃ�����̂ł��B
�@�Ȃ��A�����@�l���̌y���ŗ�15���i����800���~�ȉ��j�́A���u����Ă��܂��B
���������p���x�̌�����
�@����28�N4��1���Ȍ�Ɏ擾���錚�������ݔ��y�э\�z���̏��p���@�ɂ��āA�藦�@��p�~���A��z�@�i�z�Ɨp�͐��Y�����@�Ƃ̑I���j�Ɉ�{��������̂ł��B
���������J�z�T���̕������ɂ�錩����
�i�P�j�������̍T�����x�z�́A����28�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x���珊����60���i���s�F65���j�A����29�N�x�J�n55���i���s�F50���j�A����30�N�x�Ȍ�J�n50���i���s�F50���j�ƈꕔ��������Ă��܂��B
�@�Ȃ��A�����@�l���ɂ��ẮA�]���ǂ���A�T�����x�z�͏�����100���A�����āA�������̌J�ߊҕt�͑��u����Ă��܂��B
�i�Q�j����30�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x����A
�@�@�@�@�F�������̌J�z����
�@�@�@�A�F�������̍T�����x�ɌW�钠��ۑ�����
�@�@�@�B�������ɌW��X���̊��Ԑ���
�@�@�@�C�������ɌW��X���̐������Ԃ�10�N�i���s9�N�j�ɉ�������
�@�@�Ƃ��Ă��܂��B
�����z�������p���Y�̓���ɂ���
�@������Ǝғ��̏��z�������p���Y�̎擾���z�̑����Z���̓���ɂ��āA�ΏۂƂȂ�@�l����펞�g�p����]�ƈ��̐���1,000�l����@�l�����O������A���̓K�p������2�N�������Ă��܂��B
�����Y������ݔ��������i�Ő��̌�����
�@���Y������ݔ��������i�Ő��i���ʏ��p���͐Ŋz�T���j�ɂ��ẮA�K�p�����������Ĕp�~����B�܂��A��悹�[�u�ɂ��Ă��A����28�N3��31���Ƃ���Ă���K�p�������������Ȃ��A�Ƃ��Ă��܂��B
�����̑��̉���
��Ƃ́u�҂��́v�A�u�U�߂̌o�c�v���㉟�����邽�߁A�������^�ɂ����鑽�l�Ȋ�����V���̓����y�ёg�D�ĕ҂ɌW��Ő��̐����Ƃ������������Ȃ���Ă��܂��B