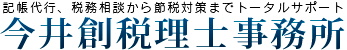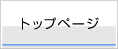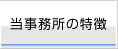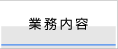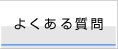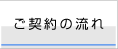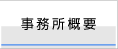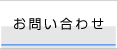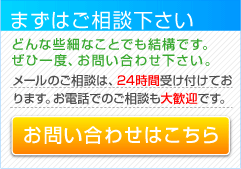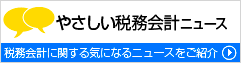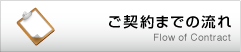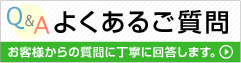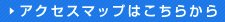税務会計に関連した気になるニュースをご紹介しています。
・第21回 未払い残業代の解決金等その課... ・第22回 所得税「半日調査」が2割増
・第23回 平成30年度税制改正 個人所得... ・第24回 事業承継税制が抜本的見直し
・第25回 小規模宅地の「家なき子」特例... ・第26回 小規模宅地の「家なき子」特例...
・第27回 生命保険の契約者変更に注意! ・第28回 相続税の改正と一般社団法人
・第29回 特例承継計画の作成上の留意点 ・第30回 2018年度税制改正:生命保険料...
・第31回 大きく変わる今年の年末調整 ・第32回 配偶者控除及び配偶者特別控除の...
・第33回 平成31年度税制改正大綱 個人... ・第34回 軽減税率制度の導入に伴う売上及...
・やさしい税務会計ニュース 第1回~第20回はこちら
やさしい税務ニュースは毎月1回更新しています。
□軽減税率制度の導入に伴う売上及び仕入税額の計算の特例とは!?
今年10月からの消費税の軽減税率制度の導入に伴い、税率の異なるごとに売上及び仕入れを区分して経理することが難しい中小事業者には、経過措置として、消費税額を簡便的に計算することができる売上税額の計算の特例及び仕入税額の計算の特例が認められておりますので、該当されます方はご確認ください。
なお、上記の特例は、中小事業者のみを対象とし、2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間に適用されます。
具体的には、課税売上(税込み)に一定の割合を乗じて計算した金額を、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)とすることができ、一定の割合として、
①軽減売上割合
②小売等軽減仕入割合
のいずれかを中小事業者の態様に応じて適用することができます。
上記①の軽減売上割合とは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税売上(税込み)のうち、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)の占める割合をいい、通常の事業を行う連続する10営業日は、この割合により計算しようとする適用対象期間内であれば、どの時点のものを用いても問題ありません。
上記②の小売等軽減仕入割合とは、課税仕入れのうち軽減税率の対象となる課税売上(税込み)にのみ要する課税仕入れの占める割合をいい、この割合により計算することができる中小事業者は、卸売業又は小売業を営んでおり、課税仕入れを税率ごとに区分経理でき、かつ、簡易課税制度の適用を受けていないことが要件とされます。
なお、軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合の計算が困難で、かつ、主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者については、軽減売上割合又は小売等軽減仕入割合を50%とみなして計算することができます。
主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者とは、課税売上のうち軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。
ただし、課税売上の大部分が軽減税率の対象となる課税売上の場合、軽減税率の対象となる課税売上を50%で計算しますと、残りの50%が標準税率の対象となる課税売上として計算され、税負担が重くなりますので、ご注意ください。
□平成31年税制改正大綱 個人所得課税(一般)編
●31年税制改正「消費税対策」が重点に
平成31年の税制改正大綱では、10月に実施予定の消費税率10%引上げに伴う、駆込み需要・反動減対策(車両・住宅)に重点が置かれ、単年度ベースで1,670憶円規模の減税措置がされると公表されました。
個人所得課税(金融・証券税制以外のもの)については、次の項目が改正されます。
●住宅ローン控除の拡充(国税・減税)
過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。
1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)
11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(最大4000万円)×2%÷3
●空き家の譲渡の特別控除(国税・減税)
適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。
●ひとり親(未婚)の非課税(住民税・減税)
自公で議論となっていたのが、婚姻歴のないシングルマザー等の「寡婦(夫)控除」の取扱い。結論は翌年に持ち越しとなりましたが、次の要件を満たす「ひとり親」の住民税が非課税とされました(未婚男性の「ひとり親」にも適用されます)。
・児童扶養手当の支給を受けていること
・前年の合計所得金額が135万円以下
なお、所得税の負担が残るため、給付金17,500円(非課税)が年収365万円までの10万人弱を対象に支給される見通しです。
●その他の改正(ふるさと納税の適正化など)
その他には、①ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、②仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、③申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、④森林環境税(仮)の創設、⑤公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。
□平成31年度税制改正大綱 個人所得課税(金融・証券)編
●金融庁要望の「NISA恒久化」は持越し
平成31年度の税制改正大綱では、消費増税への対応に比重がかけられたため、金融・証券税制の分野については、脇に置かれた感があります。金融庁が要望していた「NISA制度の恒久化」「金融所得課税の一体化」などは実現に至りませんでした。
それでも、①NISAの利便性向上(海外赴任時の継続利用・利用開始年齢の引下げ他)、②投資信託等の内外の二重課税の調整措置、③レポ取引に係る利子の非課税措置の延長、④マイナンバーに関する所要の措置などが改正される予定です。
●NISA口座保有者が出国した場合の特例
NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は、国内居住者の少額投資を非課税とする制度としてスタートしたため、居住者が海外転勤等により一時的に出国する場合には、NISA口座で保有している金融商品は一般口座(課税口座)に払い出されていました。また、帰国後においても、一般口座に一旦払い出された金融商品をNISA口座に戻すことはできませんでした。
そこで、次の手続きを行った出国者については、国内居住者とみなしてNISA口座を最長5年間にわたり、継続利用できることとしました。
(一時的な出国による場合の特例)
◎継続適用届出書の提出:出国日の前日までに取扱金融機関に転任の命令その他やむを得ない事由により出国する旨等を記載した継続届出書を提出
◎帰国届出書の提出:取扱金融機関に帰国した年月日、非課税口座に再び上場株式等を受け入れる旨を記載した帰国届出書を提出
なお、出国から帰国までNISA口座の保有はできますが、この間(最大5年間)、新規買い付けはできません。また、その出国につき「所得税の国外転出時課税」を受ける場合には、適用を受けることはできません。
●NISA利用開始年齢の引下げ・利便向上施策
民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、NISAの口座開設が可能な年齢も20歳から18歳に引き下げられることになりました。平成35年1月1日以後の口座開設より適用されます(経過措置あり)。
大綱には、その他にもロールオーバー移管依頼書の手続きの簡素化、一般NISAとつみたてNISAの切り替え手続きの簡素化など利便向上の施策が盛り込まれています。
□配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを公表!
国税庁は、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を公表しました。それによりますと、14問を追加・更新するなど大幅に改定して、年末調整に向けた変更点などを解説しております。
2018年の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。2017年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額や申告書等の様式等が大きく変わりました。
2017年分以前は、申告書が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類でしたが、2018年分以後は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式と変更され、3種類になりました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する内容は、大きな変更はありません。
しかし、「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載することになりました。
2017年度税制改正において、納税者本人に所得制限が設けられ、本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。
また、配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられており、2017年分以前に適用を受けられなかった人でも、2018年分より適用を受けられる可能性がありますので、ご注意ください。
2018年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますので、あわせてご確認ください。
□大きく変わる今年の年末調整
●平成30年分の所得税から控除が変わる
平成29年度の税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されることになりました。これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載事項等の見直しが行われていますので、今年の年末調整事務は注意が必要です。
●変更点1 配偶者控除の見直し
従来は所得者本人の所得金額に制限はなく、控除対象配偶者がいる場合は誰でも38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)の控除が受けられました。しかし、改正後は、所得者本人の収入に応じて控除額が逓減する仕組みが加わり、本人給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合の控除額は次のようになります。
(1)給与収入1,120万円超1,170万円以下
(所得金額900万円超950万円以下)の控除額26万円〈32万円〉
(2)給与収入1,170万円超1,220万円以下
(所得金額950万円超1,000万円以下)の控除額13万円〈16万円〉
(3)給与収入1,220万円超(所得金額1,000万円超)の控除額0円
※〈 〉内は老人控除対象配偶者の控除額
●変更点2 配偶者特別控除の見直し
対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除が受けられるよう見直されました。また、適用範囲が拡大し、配偶者の合計所得金額が改正前の「38 万円超 76 万円未満」から「38 万円超 123 万円以下(給与収入103万円超201万円以下)」となりました。一方、配偶者控除と同様に、所得者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みが加わっています。
●留意すべき事項
改正後の配偶者特別控除は適用区分が細分化され、複雑化しています。所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握しないと控除額の計算が行えませんので、配偶者特別控除申告書の記載に当たっては十分な確認が必要でしょう。また、配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額要件が拡大しましたが、社会保険の被扶養者要件は変更されていませんので、被扶養者となるためには所得調整が必要です。
気になる税務の話をわかりやすく。~やさしい税務ニュース
□2018年度税制改正:生命保険料などの年末調整手続きを電子化へ!
2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(いわゆる住宅ローン控除)に係る年末調整手続きを電子化することが盛り込まれております。
現行、住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除を適用するには、年末のローン残高証明書や保険料控除証明書を銀行や生命保険会社等から郵送で受け取り、これら紙の証明書を勤務先に提出する必要があります。
その際、給与所得者の保険料控除申告書などの関係書類を作成して一緒に提出する必要があり、会社や社員からは、一連の手続きが非常に煩雑であるとの声がありました。
年末調整手続きの電子化では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書の5つの年末調整関係書類の書面による提出に代えて、電磁的方法による提供(電子提供)をすることができるように電子化します。
この目的は、インターネット上で簡単に手続きができるようにすることで個人や企業の利便性を高め、事務負担の軽減を図ることです。
そして、これらの見直しとともに、住宅ローン控除申告書等に添付すべき住宅ローン控除証明書、年末残高証明書については、それらの証明書の発行者から電子メール等により提供を受けたその住宅ローン控除証明書、年末残高証明書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものであれば、住宅ローン控除申告書等に添付することができるようになります。
これらの改正は、2020年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書や住宅ローン控除申告書について適用します。
なお、住宅ローン控除証明書と住宅ローンの年末残高証明書の電子データによる提出は、居住年が2019年以後である者に限られます。
今後、年末調整手続きの電子化は、保険会社や銀行等の控除関係機関から個人、税務署、雇用主という情報の流れが、基本的にネット上で完結する仕組みになるとみられております。
今後の動向に注目です。
□特例承継計画の作成上の留意点
はじめに
中小企業経営者の高齢化に伴い、今後10年の間に平均引退年齢である70歳を超える経営者が245万人になると推定されています。このうち、半数以上が事業承継の準備を終えていない現況にあります。そこで、平成30年度税制改正では、円滑な世代交代に向けた集中取組み期間(10年間)の時限措置として、事業承継税制の各種要件の緩和を含む事業承継税制の特例制度が創設されました。
本稿では、事業承継税制の特例の適用を受ける場合に必要となる特例承継計画の作成上の留意点について解説することとします。
Ⅰ 定義(円滑化規16①)
「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、その特例認定承継会社の後継者及び承継時までの経営見通し等が記載されたものとされます。
Ⅱ 確認申請書の提出(措法70の7の5②)
平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画の確認申請書(様式第21)」による申請書に、その申請書の写し1通及び登記事項証明書(確認申請日の前3月以内に作成されたものに限り、特例代表者が確認申請日においてその中小企業者の代表者でない場合にあってはその特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含みます。)を添付して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出します。
Ⅲ 記載事項
特例承継計画の主な記載事項は、次に掲げるとおりとされます。
① 会社:主たる事業内容、資本金額等の総額、常時使用する従業員の数
② 特例代表者:申請者の氏名、代表権の有無(「無」の場合は、退任した年月日)
③ 特例後継者:株式を承継する予定の後継者の氏名(最大3人まで)
④ 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画:株式を承継する時期、経営上の課題、その課題への対応
⑤ 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画:各年の取組内容、期待できる効果
⑥ 認定経営革新等支援機関による所見等:事業承継を行う時期、準備状況、事業承継時までの経営上の課題とその対処方針、事業承継後の事業計画の実現性などの指導・助言の内容
Ⅳ 都道府県知事の確認(円滑化規17④)
都道府県知事は、上記Ⅱの申請を受けた場合において、その確認をしたときは「施行規則第17条4項の規定による確認書(様式第22)」を申請者である中小企業者に対して交付します。また、その確認をしない旨の決定をしたときは「施行規則第17条4項の規定による確認をしない旨の通知書(様式第23)」により申請者である中小企業者に対して通知します。
Ⅴ 特例承継計画の認定(円滑化法12①,円滑化規7⑥)
特例承継計画の認定を受けようとする特例認定贈与承継会社は、その認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに、「第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(様式第7の3)」による申請書に、その申請書の写し1通及び上記Ⅳに掲げる確認書(様式第22)等の一定の書類を添付して、都道府県知事に提出することとされます。
おわりに
特例承継計画に特例後継者として氏名を記載された者でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできません。また、特例承継計画を提出した場合であっても、特例後継者に株式の承継を行わなくても罰則規定はありませんので、実務上は期日までに特例承継計画の提出をしておくべきでしょう。
なお、特例承継計画の確認を受けた後に、計画の内容に変更があった場合は、変更申請書(様式第24)を都道府県に提出し確認を受けることができます。この変更申請書には、変更事項を反映した計画を記載し、再度認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることが必要とされます(円滑化規17①一,同規18①⑤)。
ただし、既に特例認定贈与承継会社の株式の贈与を受けた特例後継者については、変更対象者とされませんので留意して下さい。
□相続税の改正と一般社団法人
●一般社団法人等を使った相続対策とは…
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された2008年以降、一般社団法人の設立が容易になりました。
そこで、一般的な方法としては次のような相続対策が急増しました。
(1)一般社団法人を設立する。
(2)そこに被相続人所有の不動産や自社株を移動します。
(3)相続人を理事又は理事長とする。
(2)の段階で問題となったのは、不動産や自社株を時価で売却した場合、被相続人にかなりの譲渡所得が発生したり、高額な貸付金や金銭が手元に残ったりすることでした。
しかし不動産や自社株は所得税の分離課税であり、課税は20%強で済みます。また高額な貸付けは不動産収益や配当での返済や、親族理事への報酬により赤字にして債務免除することも可能でした。
更に非営利法人として認められた場合は、寄附や贈与も課税対象から外れていました。そしてこのようにして一般社団法人に移された財産は、相続財産から完全に除かれておりました。
●今回の改正では…
同族関係者が理事の過半数を占める特定一般社団法人等については、同族理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合は、その特定一般社団法人等を個人とみなして、同族理事の数で等分した当該特定一般社団法人等の財産を、死亡した理事から遺贈により取得したものとみなし相続税を課税するというものです。更に既にある一般社団法人等についても、特定一般社団法人等に該当すれば、平成33年4月1日以後の理事の死亡については適用するというものです。
対策としては次の事が考えられます。
(1)被相続人対象者が理事を辞め5年を超えて長生きすること。
(2)同族理事の数を50%以内とする。と同時に被相続対象者は3年を超えて長生きすること。
(3)(1)(2)ができない時は逆に同族理事の数を増やし等分財産を少なくする。
しかし特定一般社団法人等に該当しなければ従来通りですから、これで相続対策がなくなるとは思えません。
□第27回 生命保険の契約者変更に注意!
2015年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため、2018年1月1日以後の生命保険の契約者変更は税務署に把握されます。
保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできませんでした。
しかし、同制度の見直しにより、契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係にご注意ください。
例えば、親が契約者で子が被保険者というケース、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われませんが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書も提出されないこともあって、国税当局による把握も難しいとされておりました。
その影響もあってか、2015年度税制改正において生命保険に関する調書制度の見直しが行われましたので、2018年1月1日以降の生命保険の契約者変更は税務署に把握されております。
また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになります。
その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。
その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されますので、あわせてご確認ください。
□第26回 配偶者(特別)控除の変更点
●平成30年から改正適用となります
今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。内容をおおざっぱに言うと「配偶者特別控除適用上限が140万円ではなくなった」ということになります。
ただし、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得金額によって、配偶者控除や配偶者特別控除の額が増減します。
●本人の所得によって変動する配偶者控除
まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。
①本人の合計所得が900万円以下(給与収入のみで計算すると1,120万円以下)の場合→配偶者控除は38万円
②本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合→配偶者控除は26万円
③本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合→配偶者控除は13万円
④本人の合計所得が1,000万円を超える場合→配偶者控除は適用されません
※配偶者の所得はいずれも38万円以下(給与収入103万円以下)であることが条件
●配偶者特別控除の変動
今までは38万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが、今回の改正によって本人の所得により、そのパターンが3つに分かれました。また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで(給与収入のみで換算すると201万円まで)となる他、配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)までは配偶者控除と同額の控除額となります。
・本人の所得900万円以下 →配偶者特別控除額:38万円~3万円
・本人の所得950万円以下 →配偶者特別控除額:26万円~2万円
・本人の所得1,000万円以下 →配偶者特別控除額:13万円~1万円
※本人所得が1,000万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない
●「103万円の壁」は無くなったが……
妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、税金によって手取り額に差が出てしまう現象を「壁」とよく言いますが、最大の「壁」というのは「社会保険料負担」が発生することです。
この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。社会保険料関係の法改正も早急にして欲しいですね。
やさしい税務ニュースは毎月1回更新しています。
□第25回 小規模宅地の「家なき子」特例厳格化
2018年度税制改正大綱で、不動産を使った代表的な相続税対策である「小規模宅地特例」について、適用要件が厳格化されることになりました。同特例は、一定規模以下の宅地にかかる相続税評価額を引き下げる制度。被相続人が住んでいた土地なら330平方メートルまでの部分の課税価格が8割、貸付事業に使っていた土地なら200平方メートルまでの部分の価格が5割、それ以外の事業のための土地なら400平方メートルまでの価格が8割引となります。
制度の本来の趣旨は、住んでいた家を相続税負担によって出ていかざるを得なくなることにならないよう、宅地に大幅な評価減を認めることで残された家族の生活を守るものです。ただし親から宅地を相続する子が親と同居していなくても、持ち家がない時には、特例が適用されることになっています。
そこで、子がもともと持っていた自分の家を親族らに贈与した上で借り受け、形式上の「家なき子」となって特例措置を使う税逃れが横行していました。特例適用による税収減の概算は16年度で1350億円と、3年で実に倍近くまで伸びているのが実情です。
こうした経緯を踏まえ18年度大綱では、(1)相続開始前3年以内に、3親等以内の親族か関係のある法人が所有する家に住んでいたことのある人、(2)相続開始時に住んでいた家を、過去に所有していたことがある人――については、小規模宅地の特例を認めないとしました。見直しの内容は18年4月以降に相続や遺贈で取得した宅地に適用されます。大綱では、「本来の趣旨を逸脱した悪用を防止する」と強い口調で、見直しの理由を説明しています。
□第24回 事業承継税制が抜本的見直し
2009年に創設されて以降、毎年のように小さなリニューアルが施されてきた「事業承継税制」に、ついに抜本的な見直しが図られます。中小企業の経営者の高齢化がとまらず、事業承継が進まないなかで、税制面から強く後押しをすることで、一挙に世代交代を図りたい狙いです。
これまでの事業承継税制は、先代から後継者に自社株を相続・贈与で引き継ぐ際に、譲り渡した自社株と後継者がもともと持っていた自社株の合計のうち発行済議決権株式の3分の2までの部分を、相続税なら評価額の8割、贈与税なら全額を納税猶予するというものでした。
18年度改正大綱では、まず、これまで最大でも発行済議決権株式の3分の2までしか猶予できなかったところを、100%に引き上げました。また相続税なら評価額の8割が上限であったところを、これも10割まで拡大します。仮に評価額6千万円の株式を持ち株ゼロの後継者に相続で渡したとすれば、3分の2×8割=3200万円までしか猶予されなかったところが、6千万円全額について猶予されることになるわけです。
また経営が悪化して雇用を維持でなくなっても、認定支援機関など専門家の意見を記載した書類を提出することで、猶予を打ち切られずに済みます。その他、これまで後継者は1人のみを選ぶことを求めてきましたが、複数人への自社株引き継ぎにも利用できるようになります。
大綱では10割の猶予を認める見直しを中小企業の世代交代のための「特例措置」として位置付け、その期限を10年間と切っています。具体的には、18年1月1日から27年12月31日までの間に引き継がれた自社株についての相続・贈与が対象となります。
□第23回 平成30年度税制改正 個人所得課税編
平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。先ず、個人所得課税から主な改正内容を概観してみます。なお、これらの改正は、平成32年分以後の所得税からの適用となっています。
●給与所得控除等
次の見直しがなされています。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を
195万円に引き下げる。
また、特定支出控除の範囲も、次のような見直しがなされています。
(1)職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。
(2)単身赴任者の帰宅旅費1月4往復の制限を撤廃する等。
●公的年金等控除
次の見直しが行われています。
(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、
195万5千円を上限とする。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
上記(1)または(2)の見直し後の控除額からさらに一律10万円、2,000万円を超えると一律20万円、それぞれ引き下げる。
●基礎控除
次の見直しがなされています。
(1)控除額を一律10万円引き上げる。
(2)合計所得金額2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて逓減し、
2,500万円を超えると適用できないこととする。
●所得金額調整控除
この控除は、(1)給与等の収入金額が850万円を超える場合であっても、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象者が同一生計にいる場合には負担増とならないように、また(2)給与等と公的年金等の両方の収入がある場合、それぞれの所得計算の段階で控除額が10万円引き下げられると計20万円の引き下げとなり負担増となる、これらを調整するため新たに設けられた控除です。
●青色申告特別控除
この控除は、55万円に引き下げられますが、次の追加要件を満たすことで現行の65万円控除が受けられます。
(1)電子帳簿の作成及び保存、又は
(2)所得税の確定申告書を電子申告していること。
□第22回 所得税「半日調査」が2割増
国税庁によると、2016年7月~17年6月に実施した所得税の税務調査は64万7144件で、前年からわずかに減少しました。そのうち、短期間の実地調査で非違を指摘する「着眼調査」は2万1226件で、前年から2割増えています。また文書や電話によって来署依頼をする「簡易な接触」は前年よりわずかに減少したものの、約58万件と調査件数全体の9割を占めました。脱税の手口なども複雑化するなかで、短期に集中的な調査を行って実績を上げている状況がうかがえます。
税務調査の種類は大きく4つに分けられます。まず高額、悪質な脱税などに時間を掛けて取り組む「特別調査」があり、これには着手から終了まで数カ月かかることも珍しくありません。次に、下調べの上で数日かけて現場で調査を行う「一般調査」があり、税務調査と聞いて思い浮かべるような最もスタンダードな手法がこれです。さらに短く、半日ほどの現場調査で終える「着眼調査」があり、この3手法を合わせて、現場に赴く「実地調査」と呼ばれます。唯一、実地調査に当てはまらないのが、文書や電話によって来署依頼をするなどの方法によって申告を修正させる「簡易な接触」で、これは税務調査の法的手続きが厳格化された2013年以降、激増しています。
国税庁によれば、今年6月までの1年間に行われた約65万件の所得税調査のうち、「特別調査」と「一般調査」の合計は4万9012件で、前年より1千件ほど増加しています。注目したいのは3つ目の「着眼調査」で、前年1万7973件だったところが、今年は2万1226件と、一気に2割増加しました。
国税庁は近年になり、重点的に取り組むテーマとして税務調査の〝選択〟と〝集中〟を挙げていて、高額な不正が見込まれる案件には人や時間などのリソースを大量投入する一方で、それ以外の軽微な不正については省力化を図っていくというメリハリ化に取り組んでいます。半日程度で終わる着眼調査の増加は、国税のそうした姿勢の表れと言えそうです。

□第21回 未払い残業代の解決金等その課税関係
元従業員(被用者)からの未払い残業代請求の訴えが、突然、裁判所から送られて来ることがあります。多くの場合は、労働審判への申立て手続きによるもので、裁判官、労働者側、経営者側の3者が双方から提出された証拠資料等を吟味して、3回の審議で結論を出すことになっています。
●一括支払いの和解金又は解決金
労働審判は、個別的労使紛争が対象です。それ故、集団的未払い残業代の訴えのように、正確な各月の残業代を計算し、各年分の年末調整をやり直す等幾つもの諸手続きを想定していません。双方が合意できる金額での早期決着が眼目ですから、調停成立の文言も、「本件解決金(又は本件和解金)として〇〇〇万円の支払義務がある」といった例は散見されます。まさに、ザックリとした金額です。
●名目としての解決金、和解金の実質は
文言のニュアンスからは、当該解決金等は非課税であるかのような印象も受けますが、やはり審判所への訴えが「未払い残業代」、ということですので、在職中の給与等の追加払い、ということになり、原則、給与所得を構成するのではないかと考えます。
この場合、未確定であった在職中の給与等の追加払いを一時に受けることから、その受けた年の「賞与」としての扱いになるのではないかと考えられます。
●支払者(事業主)の手続き
事業主は、当該解決金が未払い残業代に相当すれば、当然に、その支払いの際には源泉徴収義務を負い、源泉税徴収後の金額を被用者に支払います。
なお、被用者が源泉徴収すべき税額を含めて強制執行等により未払い残業代全額の回収を求めてきた場合、事業主は解決金の全額を支払う義務を負うことになります。
但し、その場合であっても、法的には、事業主の源泉徴収義務は免れることはできません。事業主は、源泉徴収義務者として解決金〇〇〇万円に相当する源泉税を計算し納付しなければなりません。
そうすると、事業主は、二重に源泉税分を支払ったことになりますので、その分、被用者に請求することができますが、被用者が無資力の場合はその回収は困難です。
審判所においても、未払い残業代に伴う源泉徴収税額を双方協議しておくのが望ましいように思います。